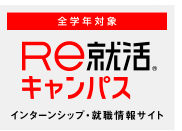COLUMNショクブン通信
食のプロが、おいしい料理のコツをアドバイスします。
-
 レシピ
レシピ
【薬膳料理家監修】お体メンテナンス 免疫力を上げる季節の養生3月
春は冬の間にため込んでいた気のエネルギーを全身に巡らせ、
カラダの中の老廃物を外に出す季節です。
エネルギーの巡りが悪いと、自律神経の乱れを招きます。
イライラ感や頭痛、肩こりなどの症状も出てきます。
「ゆるめ上手」を心がけることがこの時期の養生のコツ。 -
 レシピ
レシピ
【薬膳料理家監修】お体メンテナンス 免疫力を上げる季節の養生2月
2月4日は立春。暦の上では春ですが、寒暖差が激しく自立神経が乱れがちです。
季節の変わり目は体調を崩しやすいので、冬の養生も行いつつ、春に向けてカラダの準備をしていきましょう。 -
 レシピ
レシピ
【薬膳料理家監修】お体メンテナンス 免疫力を上げる季節の養生1月
新年がスタートしましたね。
「寒の入り」は最も気温が低くなる時期です。
カラダを冷やさないよう心がけましょう。
年末、お正月で食べすぎてしまった時は胃腸のケアも大切です。
寒い冬にパワーを充電して、春からの1年を快適に過ごせるようにカラダを整えていきましょう。 -
 レシピ
レシピ
【薬膳料理家監修】お体メンテナンス 免疫力を上げる季節の養生12月
今年も残りわずかになりました。
みなさんはどんな1年を過ごしたでしょうか。
年末はバタバタと忙しくなりがちですが、
冬は1年分のエネルギーを蓄える季節です。
無理をせず体調に気をつけて、
バランスのとれた食事と休養を心がけましょう。 -
 レシピ
レシピ
【薬膳料理家監修】お体メンテナンス 免疫力を上げる季節の養生11月
暦の上では冬の始まり。だんだんと寒くなってきますね。
冬は寒さから身を守るため、夏よりもエネルギーを多く使います。
また、人間の生命力のバッテリー電池は「腎」にあります。
カラダを温めるものをとり、腎の養生を心がけましょう。 -
 レシピ
レシピ
【薬膳料理家監修】お体メンテナンス 免疫力を上げる季節の養生10月
秋も深まり、スポーツの秋、そして食欲の秋ですね。
過ごしやすい季節ですが、朝晩と日中の気温差によって体温調節が難しく、体調も崩しやすくなるので注意が必要です。
夏の疲れが残っていると秋バテの症状(疲れやすい、よく眠れない、食欲がないなど)も出てくるので気をつけましょう。 -
 レシピ
レシピ
【薬膳料理家監修】お体メンテナンス 免疫力を上げる季節の養生 9月
日中の暑さは残りますが、朝晩はだんだんと涼しくなる季節。空気が乾燥するので「肺」に負担がかかり、のどや鼻の粘膜に炎症を起こしやすくなります。さらに、秋は寂しさを感じて気分が落ち込みがちに。カラダの気の流れも悪くなるのでリフレッシュできる時間をつくりましょう。また、夏の疲れが出やすい胃腸のケアも大切です。
-
 レシピ
レシピ
【薬膳料理家監修】お体メンテナンス 免疫力を上げる季節の養生 8月
8月は夏の暑さや発汗から体力の消耗を感じ、夏の疲れが出やすい時期です。特に、胃腸の働きの低下を感じるかもしれません。食欲がない、疲れやすい、カラダがだるいなどの症状が出てきます。そのため、中国医学では特に胃腸のケアが必要な時期といわれています。しっかりとカラダのケアをして、秋に疲れが出ないように整えていきましょう。
-
 レシピ
レシピ
【薬膳料理家監修】お体メンテナンス 免疫力を上げる季節の養生 7月
7月はだんだんと気温が上がり、梅雨から夏に移り変わる時期。冷房を使うことによる冷えや夏のむくみにも気をつけながら、これから訪れる本格的な暑さに向けて夏バテや熱中症の予防も大切です。今回は、気カ・体力の消耗を防ぐための養生法をこ紹介します。